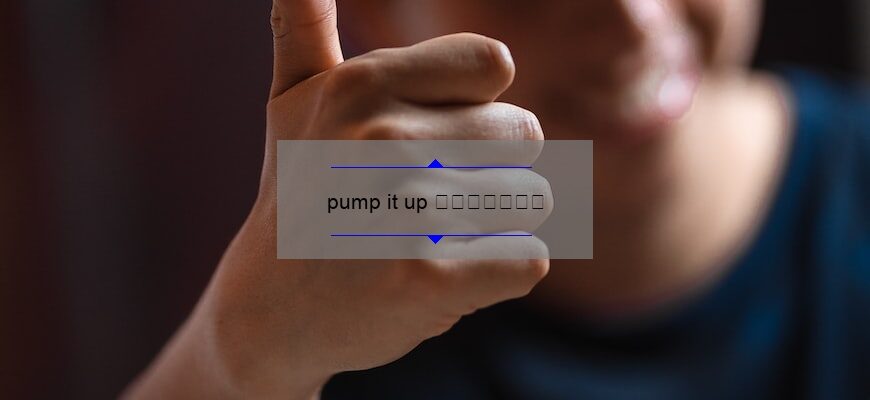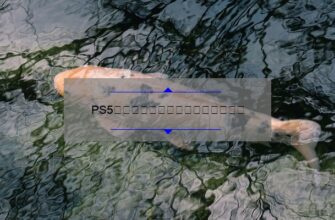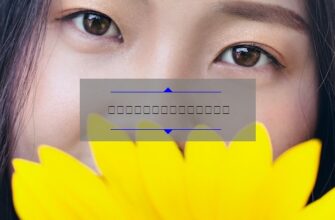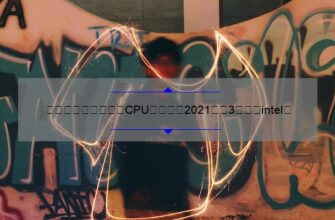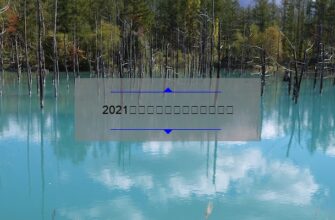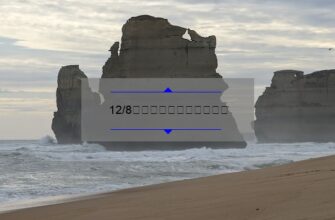先日のPump it upの感想記事がかなりの人に見てもらえたことからやはりPIUをやってみたい人は潜在的に多いということが分かりました。そこで、今回の記事はそんなPIUを更に面白くするために必要なアンダミロのアカウント取得の方法についてまとめていきたいとおもいます。
PIU 2019 20TH ANNIVERSARY – DOUBLE X
Pump it Up公式サイト URL
まずは、Pump it upの公式サイトにログインをします。
注意!
この際に言語の設定を日本語ではなく、英語か韓国語に設定しましょう。日本語だと最後の画像認証ができず登録ができません。英語だと翻訳機が使いやすいのでここでは英語の画面を使いたいと思います。
赤丸のPIU joinのところからアカウントの登録作業を進めます。このボタンを押すと規約への同意のチェックがあるので、チェックをしてから登録作業を進めます。
記入欄
黒い三角がついている事項が必須項目ですので、そこに情報を加えましょう。黒い三角がない場所は任意の記入ですので、入れたくない場合は未記入でも問題ないです。
E-mail→gmailでも大丈夫でした
zipcode→郵便番号
Date of birth→誕生日、ハングル文字がありますが月と意味ですのでそこまで構えなくても大丈夫です
state/province→県の名前を記入すればOK?
Auto register provention numbers→ここが日本語版だとバグっていて登録ができませんでした。
その他、性別を選ぶ欄がバグっていて選べませんでしたが登録自身には何も影響はありませんでした。
次はカードとアンダミロアカウントとの紐づけを行います
set representativeのボタンをクリックします
すると
一つのアカウントには三つのカードを登録できるのでこのような画面が出てきます。
AM.PASSとUSBのどちらでアカウントを登録したいか選べます。
AM PASSというのはこのようなカードです。日本のe-AMUSEMENT PASSやaimeなどとは当たり前ですが、対応していないの注意しましょう…
あまりカードを持っている人はいないと思うので今回は、USBで登録をする場合の方法を書いておきます。USBを刺した状態でUSBの下のConfirmのボタンを押すとしたの画面が出てきます。この画面は自分のIDのネームを登録する画面です
要はゲームで出てくる名前を決める画面です。PIUのユーザーネームは一度決めると二度と変えられないので注意しましょう。
数字と半角の文字しか使えません。ユーザーネームを決めた後はcheckボタンを押して使えるユーザーネームかを判断します。
使える名前で、気に入った名前ならばConfirmボタンを押して登録を完了させましょう。
最後に、上記のような画面になったらDownloadのボタン(日本語版ならアクセスコードの発行)を押すと、ログインをするためのファイルをダウンロードできるので、そのファイルをUSB直下の場所に置きましょう。このようにすれば筐体でも認識できるようになり、ログインしてプレイをすることができます。
ちなみにAM PASSに変えることもできるようです…
以上で登録完了です。
より良い踏みゲーlifeを!